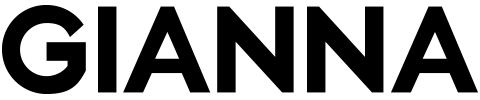日本の美術のなかでも、「襖絵」や「屏風絵」は、空間と一体となって美を紡ぎ出す独特な芸術です。光の変化や時間の流れとともに表情を変え、見る者を深い世界へと誘います。本企画では、現代を代表する三人の絵師に焦点を当て、彼らが筆を通じて表現する世界観と、伝統を現代に継承する姿勢を探求します。

枠を超えて線は走る ── 木村英輝、描き続ける「生命のエネルギー」
動植物たちの躍動を、太い「線」と鮮やかな「色」で描き出す絵師・木村英輝。モチーフに宿る生命力、空間との対話、そして壁や天井という制約を超えてあらわれる奔放な表現。幼少期に道端で絵を描いた原体験、ロックとの深いかかわり——その根源にある衝動は、時代やジャンルの枠を自在に越え、命のリズムを響かせ続けている。絵を描くことは、生きること。80歳を超えた今もなお、筆を走らせる木村が見つめているのは、過去でも未来でもなく、今この瞬間に脈打つエネルギーだ。大胆に、軽やかに、そして真摯に。生命の鼓動をとらえるその旅に、私たちも歩みを重ねてみたい。
INTERVIEW
はじめに、木村さんがアートに触れた原体験について教えてください。
子供のころ、よく道端で絵を描いていました。それが私の絵の原点です。人前で描くのが好きで、褒めてもらえることが嬉しくて、自由に描いていましたね。こうした幼少期の経験が、今につながっています。
京都市立美術大学(現:京都市立芸術大学)をご卒業されたそうですが、図案科を選んだのはなぜですか?
私は大阪の泉州、泉大津の出身なんです。あのあたりは、とても現実的な土地柄で、「画家になりたい」と口にしようものなら、すぐに「貧乏絵描きさん」と見なされてしまうような雰囲気がありました。だから、私は絶対に画家にはならないぞ、と。商売につながる絵を描こうと思って、図案科を選びました。
影響を受けたアーティストはいらっしゃいますか?
学生時代は、ちょうどアンディ・ウォーホルが登場した時期でした。それまでのアートの概念が根底から覆されましたね。「目の前にあるコカ・コーラの瓶こそがアートだ」とか、「本物のリンゴよりも、テレビに映っているリンゴのほうが本物だ」なんてことを、みんなが言い始めた時代です。ウォーホルはもちろん、ロバート・ラウシェンバーグやロイ・リキテンスタインといったアーティストたちには、本当に大きな影響を受けました。
アンディ・ウォーホルは、制作や販売のスタイルも革新的でしたが、そういった点にも影響を受けましたか?
そうですね。従来のやり方にとらわれず、制作過程もオープンにして、それ自体を作品と見なすといった考え方は、とても面白く感じました。彼は、もともとデザイナーでしたから、「デザイナーがアートを手がける」という流れを作ったことにも共感しています。 アートは本来、人間の本質に問いかけたり、表現したりするものだと思っています。しかし、いつの間にか、社会からかけ離れた、驚きを狙うだけの「衒い(てらい)」のようなものになってしまった部分があるように感じていて……。私は、アートはもっと人間とつながっていくべきものだと思っています。
大学卒業後に、音楽プロデューサーになられた経緯を教えてください。
大学卒業後、非常勤講師として大学に残りました。しかし、当時は1965年から70年の安保闘争に向かう時代で、多くの大学がバリケード封鎖され、ほとんど授業がありませんでした。そんな状況だったので、「街に出よう」と決めたんです。寺山修司さんが「書を捨てよ、町へ出よう」と言ったように、私たちも街に出て、何かを表現しようと。そこでさまざまな集会を始めました。その集会にたまたま、山口冨士夫さんのようなミュージシャンが参加してきて。ちょうどグループサウンズが終焉を迎え、実力派のバンドが台頭してきた時期でした。フォークシンガーも多くいましたが、エレキギターを持ったバンドはひときわ目立っていました。そのうちに、私たちの集会がまるでロックフェスのように変わっていったんです。それが、ロックにかかわるようになったきっかけですね。
当時の海外におけるロックフェスの状況はいかがでしたか?
ウッドストックや、オルタモント、ワイト島といったフェスが、私たちの活動より少し前にありました。1967年から68年頃ですね。私たちは、1968年から69年にかけて、似たようなことを始めたんです。もともとロックフェスを企画していたわけではありませんでしたが、これら海外フェスの影響を受けて、私たちの集会も徐々にフェスのような形式へと変化していきました。
なるほど。長年音楽プロデューサーとして活躍 された後、還暦を過ぎてから絵師としての活動を始められたそうですね。その背景には、どのようなお考えがあったのでしょうか?
長年、ロックイベントのプロデュースに携わってきましたが、心の中では「もっと直接的に何かを生み出すことに挑戦したい」という思いがありました。60歳を目前にした時、その思いが強くなり、自分の原点である「絵を描くこと」に戻ろうと決意したんです。
絵画にもさまざまな形式がありますが、キャンバスではなく壁画を選ばれた理由は?
それは、最初に話した幼少期の経験が関係しています。もともと、キャンバスに絵を描くのがあまり好きではなくて、枠からはみ出すような表現をしたいと思っていたんです。その点、壁画はまさにうってつけでした。たまたま、後輩の友人が新しいオフィスを作ることになり、「壁に絵を描いてくれないか」と頼まれたので、そこに描くことにしました。
その処女作は、どのような作品でしたか?
サイの親子を描きました。当時、サイケデリックなアートが流行っていたので、最初は縁を金色に、中をショッキングピンクにしてサイを描き始めました。しかし、部屋の中にドイツ風の柱が立っていたため、どうにも雰囲気が合わない。そこで、柱の色に近い焦げ茶色でショッキングピンクを塗りつぶしたんです。完成後、友人に見せたところ「かっこいい」と好評で、これを自分のスタイルにしようと決めました。
木村さんの作品は、鯉や象、孔雀など、モチーフ選びもユニークだと感じます。どのようにしてモチーフを選んでいらっしゃるのでしょうか?
壁画を描くときは、できるだけ縁起の良い、ラッキーなモチーフを選ぼうと思っています。いつも心がけているのは、「風通しのいい絵」「光が差し込んでくる絵」を描くことです。光や風が感じられるような、見る人の心に希望をもたらすような絵を目指しています。
壁の大きさにもよると思いますが、制作にはどのくらい時間がかかりますか?
一度描き始めると、すごく早いんです。小さな下描きは用意しますが、現場では直接、壁の大きさに合わせて描いていきます。竹の棒にチョークをつけた道具で描くのですが、これは、幼少期に道端で等身大の絵を描いていた経験から来ています。その時の感覚が体に残っているので、今でも大きな絵をバランス良く描くことができるんですよ。
色を選ぶ際の基準や、特定の色に込める意味などはありますか?
私たちが目にしている色は、光が反射した色であり、その奥には別の色が隠れていますよね。そうした色の原理を意識しています。とくに、補色(反対色)の関係を重視していて、たとえば黄色と紫、スカイブルーとピンクといった組み合わせを、かっこよく表現したい。派手になりがちな反対色を、下品にならないよう洗練された形で表現することを心がけています。
制作時は、音楽を流されますか?
色を塗る時は、ディープ・パープルやレッド・ツェッペリンのようなハードロックを聴くことが多いです。一方、形を描くときは、エルヴィス・プレスリーのようなボーカルが力強い曲が気分に合います。
制作を進める上で、大切にしている美意識や哲学があればお聞かせください。
いつも考えているのは、「柳のように、体の赴くままに」という姿勢です。無理に何かを決めたりせず、自然体で物事を進めていくのが一番良いと思っています。
その考え方は、多くのミュージシャンの方々とかかわってきたことも影響していますか?
どうでしょうか。音楽の世界は、絵画よりも技術やルールが多いですよね。だから、技術を習得したり、ルールを克服したりすることに多くの労力を費やします。一方で、絵画はそこまで技術やルールに縛られない。美術を先に学んだからこそ、「枠を外す」ということが自然にできるようになったのだと思います。
絵師としてのキャリアの中で、転機になった作品や出来事がありましたら教えてください。
活動を始めてからは、どんな依頼でも基本的に断らずに描いてきました。「これしか描けない」という風にはなりたくなかったからです。そんな中、辰年を前にして、龍の絵の依頼が一気に増えました。でも、私は実在しないものを描くことに抵抗があり、龍だけはずっと避けてきたんです。もちろん、先人たちが描いた龍を参考にすれば、それっぽく描くことはできます。でも、それだと“自分の龍”ではない気がして。ただ、あまりにもご依頼が多くて「さすがに、これはもったいないかも」と思いまして(笑)。そんなとき、「登竜門」という言葉がふと浮かびました。鯉が龍になるというこの物語なら、自分なりの世界観で龍を表現できるんじゃないか、と。それ以来、龍を描いてほしいというお話があった時には、必ず「登竜門」をテーマに、鯉を描くことをご提案しています。
木村さんが、作品を通して最も表現したいことは何でしょうか?
私がいちばん大切にしているのは、エネルギーを伝えることです。そのエネルギーの結果として、美しさが生まれるかどうかだと考えています。意図的に「良いもの」を描こうとはせず、夢中で筆を動かす中で、見る人がそのエネルギーの中に美しさを見出してくれることを願っています。私の絵は、子どもの絵画に近いと思います。いつまでも、子どものころ のように分析したり考えたりせずに描いているんです。子どものころ、絵を描いて褒めてもらうのが嬉しくて描き続けた延長線上に、今の自分がいるような気がします。だから、褒めてもらうとやっぱり嬉しくて、もっと描こうという気持ちになりますね。
これまで、さまざまな国や都市で絵を描かれてきましたが、街の雰囲気や人々のムードに作品が左右されることはありますか?
むしろ、海外に行けば行くほど、「自分をぶつけよう」という気持ちになります。たとえば、カナダを訪れた時のこと。日本人アーティストがカナダで絵を描くと、桜や富士山といった日本のモチーフを選びがちです。しかし、私は、あえて現地のキングサーモンをモチーフに選びました。その土地ならではの題材を描くことで、そこに自身のエネルギーや日本のエッセンスが加わり、より面白い作品が生まれると考えています。
今後、挑戦してみたい場所やコラボレーショ ンはありますか?
個人的にスポーツが好きなので、サッカー場やスタジアムのような場所に描いてみたいです。選手たちのエネルギーがぶつかり合うような空間で、その熱量を表現できたら嬉しいですね。
木村さんの作風とマッチしそうですね。先ほどカナダの話も出ましたが、海外での反応や評価について、何か感じることがあれば教えてください。
海外の人たちは、私の壁画を見て「アート」ではなく「デザイン」と表現してくれることが多いんです。「このデザイン、面白いね」と。その捉え方がすごく好きですね。私は、ファインアート(純粋芸術)という言葉をあまり信用していません。自分の口から「純粋」なんて言うこと自体、少しおかしい気がして。だから、あくまでデザイン的に絵を描くことに関心があるんです。日本では、アートを「デザイン」と捉えると失礼にあたると思っている人もいますが、私はデザインもアートも同じだと思っています。
2015年には、「琳派」誕生4百周年を記念したイベント「琳派ロック」を総合プロデュースされました。現在は、絵師としてのご活動がメインだと思いますが、音楽とのかかわりは今も続いていますか?
絵画が「空間芸術」であるのに対して、音楽は「時間芸術」ですよね。年を重ねるにつれて、この「時間芸術」が自分の生活から少しずつ減っていって、絵画のように「結果だけがそこにある」世界に、どこか物足りなさを感じるようになりました。だから、いつも「時間限定で何かをやりたい」と思っていて、その気持ちが「琳派ロック」のようなイベントの プロデュースへとつながっています。
最近、とくに力を入れているテーマや、夢中になっているモチーフはありますか?
この年齢になって、初めて、室町時代から宗達の時代にかけての日本画に強く惹かれるようになりました。現代の日本画が西洋画の影響を受けているのに対し、当時の日本画は輪郭や線を非常に大切にしていました。この点が私の創作の原点とも重なり、とても魅力を感じています。日本で漫画文化が発展したのも、輪郭を重視するこの美意識と無関係ではないでしょう。輪郭を丁寧に描けることが「絵が上手い」とされる日本の感性が、線で表現する漫画という表現を育んだのだと思います。
次世代を担う日本画家に伝えたいことがあればお聞かせください。
「日本画」や「洋画」といったジャンルにとらわれず、もっと自由に絵を描いてほしいですね。日本人が描く絵は、すべて日本画であるというくらいの広い視野を持つべきでしょう。セクショナリズムの中で議論するのではなく、もっとフラットな視点で「絵を描く」ということに向き合ってほしいと思います。専門性が深まる一方で、閉鎖的になりがちな現代において、固定観念にとらわれない自由な表現こそが、次の時代を切り開く鍵になると信じています。
最近、効率や失敗を恐れるあまり、ルールに縛られて確実性を求める人が増えている気がします。こうした風潮について、どうお考えですか?
そもそも、「失敗」という概念は、「成功」という形が決まっているから生まれるものですよね。その考え方自体がおかしいと思います。私たちは、あるべき姿から外れたものを見ると「失敗」と決めつけがちです。しかし、本来、何が失敗かなんて明確には分かりません。それを決めつけているのは、成功のイメージを持つ人の視点にすぎないのではないでしょうか。もちろん、単純なミスは存在します。しかし、創作活動において、「描いたこと自体が失敗かどうか」を判断することはできないと、私は考えています。
「アートはもっと人間とつながっていくべきもの」というお言葉もありましたが、作品を通して、人や社会にどんなメッセージを伝えたいですか?
私の作品に一貫して流れているのは、「地球を大切にしよう」というメッセージです。個人のエネルギーを表現しつつも、究極的にはこの「ラブアース」という大きなテーマを掲げています。このテーマは、これまでも作品に取り入れてきましたが、今後も私の創作活動の根幹であり続けます。
掲載作品について
青蓮院門跡華頂殿 襖絵 -蓮- 三部作
(青の幻想/生命讃歌/極楽浄土)
真っ白な襖六十面に、自分の絵でより魅力的な空間を生み出したいと願った。主題は蓮。三室からなる空間は、「青の幻想」「生命賛歌」「極楽浄土」の三部構成にしようと決める。鳥の子紙に絵の具はアクリル。現代の画材でどこまで表現できるか挑んでみたかった。古刹には、粟田山麓の景観を巧みに取り入れた名園が伝えられる。それらと調和し、やがて書院の奥の庭へと、座して見る人の心を誘うような、襖絵が生まれた。
PROFILE
絵師 木村英輝 Hideki Kimura
1942年大阪府泉大津市生まれ。京都市立美術大学図案科卒業後、同大講師を務める。日本のロック黎明期に、オルガナイザーとして数々の伝説的イベントをプロデュース。還暦より絵師に。手がけた壁画は国内外で250カ所を超える。ロックと共に歩んできた半生は躍動感あふれる画面にもあらわれる。アトリエでカンバスに向かうのではなく、「ライブ」な街に絵を描きたい。究極のアマチュアリズムを標榜する異色の絵師。作品集に『生きる儘』『無我夢中』『LIVE』など。
Edit:RYOTA KOUJIRO Text:SUI TOYA