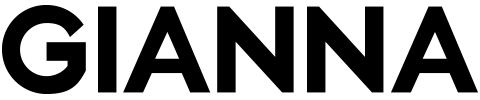華道は、四季の移ろいを尊び、自然の姿をあるがままに捉える、日本独自の美意識を象徴する芸術です。花をいけるという行為は、自己と向き合い、自然とのつながりを深く感じる、精神的な営みでもあります。本企画では、日本を代表する3人の華道家に焦点を当て、彼らが花を通じて表現する独自の世界観を探求します。

人生を映す花の力 ─ 粕谷尚弘が描く、自由な表現の可能性
一見、不安定に見える斜めの竹。それは、緻密な計算と繊細な感覚が生み出す、緊張感をはらんだ静謐な美だ。華道家・粕谷尚弘の作品には、軽やかさと力強さ、大胆な動きと繊細な手触りといった、相反する要素がしなやかに共存している。粕谷が花に見出すのは、2つとない「個性」。とりわけ、過酷な環境を生き抜いた花や枝に惹かれるのは、そこに潜む命の強さと深みのある表情に、人生そのものを重ねるからだ。伝統文化の継承者として、粕谷はいけばなの枠を広げ、花と人の関係性を再構築しようとしている。伝統と革新を行き来するその静かな挑戦は、現代における美のあり方に、新たな問いを投げかける。
粕谷さんは、幼少期より、一葉式いけ花の第三 代家元・粕谷明弘氏に師事されたそうですね。師匠から受け継ぎ、今も大切にしている教えはありますか?
「純粋に向き合うこと」ですね。生ける時に、「こうしたらすごいと思われるだろう」「上手だと思ってもらえるだろう」といった余計な思考は持ち込むな、と教わりました。大切なのは、自分が何を表現したいのか、どういけたいのかという気持ちに真っすぐ向き合うこと。そうでなければ、作品が濁ってしまうんです。自分の心に素直に従い、植物とどう向き合っていくのかを見せる。そういう姿勢が大切だと学びました。
一葉式いけ花の特徴について教えてください。
一葉式いけ花が発足する以前、いけばなの主な流派では教本を使わず、口伝で教えるのが一般的でした。そのため、上達の早い人とそうでない人との間に差が生まれ、教わる先生との相性にも大きく左右されていたのです。そこで、自由花(型にとらわれず、 草木の美をさまざまな観点から見出し、自由に生けるいけばなのこと)でいち早く教本とカリキュラムを導入したのが、一葉式いけ花の前身である「一葉式花道」でした。花を自由にいけるためには、確かな基礎が大切であり、基礎から着実に、かつ最短でステップアップできる学びの体系を整えたことが、創流当初の大きな特徴です。現在の一葉式いけ花では、「植・間(はなはざま)」という先代の教えを理念に掲げています。これは、花をいける際に自らの“間(ま)”を意識し、花の持つ魅力や表情を深く捉えようとする姿勢を表しています。
いけばなを続ける中で、ご自身にとって分岐点となった作品はありますか?
子供の頃から父の手伝いはしていましたが、いけばなを本格的に仕事にしようと考え始めたのは、大学3年生の時でした。私は次男ということもあり、家を継ぐことはないと思っていたので、周りに合わせて就職活動を始め、いくつかの企業の面接を受けたんです。ただ、私の世代はいわゆる就職氷河期。次々と不採用通知が届く中で、気持ちを入れ替えようと、公益財団法人日本いけばな芸術協会が主催する企画展「新世代展」に作品を出品しました。
どのような作品を出品されたのでしょうか?
父は竹を使った作品をよく手がけていて、私もその制作を手伝っていました。そのような中で、あるアイデアが浮かんだのです。竹は、節の位置をうまく切れば底ができて、花器として使用することができますよね。ところが、節がなく筒状になった竹は使い道がなく、ほとんどが捨てられてしまいます。内面を見られず、表面的な印象だけで価値を判断して捨てられる竹に、不採用を突きつけられる自分の姿が重なりました。筒状になった竹をよく見ると、表面はもちろん、内面も艶があって美しい。そこで竹を割り、少しずつ位置をずらしながら生けることで、外と内、それぞれの美しさが引き立つように表現してみました。自分はいけばなでもっと深い表現ができるかもしれない――この作品を作ったことで、そんな可能性を信じられるようになったのです。
一葉式いけ花では、草花や樹木だけでなく、時には金属なども花材として考えるそうですね。粕谷さんは、花材を選ぶ際にどのような基準を大切にされていますか?
花材の表情を見ていますね。よく「華がある」と言いますが、私が大切にしているのは、その“華”を花材の中に見出すことです。ここで言う“華”とは、単なる見た目の美しさではなく、言うなれば“個性”のようなもの。そういう意味で、私はどちらかというと、少しひねくれた花を選びがちですね。というのも、厳しい環境で育った花の方が、より豊かな表情を見せてくれるからです。例えば、崖っぷちで育った花は、悪条件のなかでも必死に上を目指して伸びようとします。そうした花には、凛とした強さや、勇敢さがにじんでいて、すごく惹かれるんです。その一方で、ハウス栽培でぬくぬく育った花は表情に乏しく、どこか物足りなさを感じてしまう。人間にも通じるところがあるかもしれませんね。
最近、面白い花材との出会いはありましたか?
今年(2025年)の4月末に開催された「いけばな インターナショナル第13回世界大会」のデモンストレーションでは、苔の生えた桜の木を使用しました。花屋さんが、わざわざ福島から切ってきてくださって、とてもありがたかったですね。いけばなの世界には「花は足で生ける」という教えがあります。昔の華道家たちは、自ら山や森に分け入り、花材を手にしていたんです。今では、勝手にそんなことをすれば怒られてしまいますから、代わりに花屋さんに足繁く通い、よくコミュニケーションを取ることが、面白い花材と出会うための大切な手段になっています。
「自分らしいいけばな」とは、どのようなものだと思いますか?
一葉式いけ花の作風として、軽やかさと力強さ、大きな動きと繊細さが同居していることが挙げられます。「シンプルなのに華やか」など、対極の要素をうまく調和させるようなイメージですね。私の作品は、そうしたスタイルに加えて、バランス的に“危うさ” を感じさせるようなものが多いと思います。例えば、斜めに切った竹をステージ上に立てる。そういったパフォーマンスを、限られた時間の中で見せていくんです。一見すると不安定に見えますが、実はきちんと計算した上で構成しているので、実際にはまったく危なくないんですけどね。
「危うい作品」を作られる意図とは?
物理的にアンバランスな構成にすると、作品に動きが生まれ、場に緊張が走ります。そうすることで、自然と見る人の視線を引きつけられるのです。いけばなに興味を持ってもらうためには、そうやって “過程”を見せていくことが大事だと考えています。完成した作品をいきなり見せられても、「なんとなくすごいな」で終わってしまいがちです。だからこそ、「どうやって立たせているんだろう?」「どんな形に仕上がるのかな」と、好奇心を刺激していく。そうすることで、いけばなに触れたことがない人にも、その面白さや奥深さを感じてもらえると思っています。
国内・海 外にたくさんの生徒さんを抱えていらっしゃいますが、次の世代に華道を伝えるうえで、大切にしていることはありますか?
色々なスタンスがあっていいということですね。古典的な様式を大切にされる方もいれば、前衛的な表現に取り組んでいる方もいます。そうした流派の違いがあることこそが大切だと感じています。もし、何かひとつのスタンスに統一してしまったら、逆に面白さが失われてしまうのではないかと思うのです。こう説明してもいまいち伝わりにくいので、生徒さんから「いけばなの流派にはどんな違いがあるんですか?」と質問された時は、ファッション誌に例えることが多いですね。
ファッション誌ですか?
ファッション誌には、それぞれ独自の思想や編集方針があり、それが誌面のトーンや提案するスタイルに表れていますよね。いけばなも同じで、流派ごとに特徴や考え方が異なります。一葉式のスタイルが合う人もいれば、もう少し古典的な流派を求める人もいる。「こんな見せ方もある、あんな見せ方もある」と、その多様性こそがいけばなの魅力だと考えています。
ファッションのように、華道にも“トレンド”や “流行”は存在するのでしょうか?
なんとなく、そういう流れはある気がしますね。トレンドに関しては、昔のほうがより顕著で、時代ごとのスタイルがはっきりしていたと思います。例えば、1960年代には、現代美術の影響を受けた表現が登場し、いけばなをより現代美術に近づけようとする動きが出てきました。でも、そうした表現が行き過ぎると、「これって彫刻なの?」「花をまったく使っていないけど、これはいけばななの?」という声が出てくるようになる。そうなると今度は、植物の表現に特化する流れが生まれます。腐らせた植物を使ってみるなど、植物の存在そのものに向き合う傾向ですね。そして、そういった流れがひと段落すると、「やっぱり古典的ないけばなもいいよね」と、伝統的なスタイルを好む人が増えてくるんです。そうやって、いけばなの表現も時代ごとに行き来しながら変化してきたのだと思います。
伝統を受け継ぎながらも、新しいスタイルが生まれていく。その両立は、どのように成り立っているのでしょうか?
いけばなでは、500〜600年前に確立されたスタイルが、今なお受け継がれています。そこからさまざまな新しいスタイルが生まれ、それぞれが枝葉のように分かれながら、共存している。流派同士が対立するのではなく、古典花の精神や考え方を取り入れながら、それを自由花のスタイルで表現することも自然に行われているんです。
いけばなは伝統文化というイメージが強く、どこか堅苦しいイメージを抱いていましたが、実際には、私たちが思っているよりもずっと柔軟で自由なんですね。
いけばなは、足を踏み入れてみると本当に面白い世界です。誰でも表現者になれるところも、いけばなの魅力だと思います。例えば、ダンスを習っている人は、ステップをいけばなで表現してもいい。ワインが好きなら、ブルゴーニュのワインをテーマに生けてもいい。これまでの人生で得たすべてを、いけばなに昇華させることができるのです。そこに、性別や年齢は関係ありませんし、ジェンダー観や世代観にとらわれる必要もありません。例えば、筋張った大きな手で可愛い作品を作る男性もいれば、小柄な女性がものすごく迫力のある作品を作ることもあります。手を動かすうちに、「その人らしさ」や「人生観」 が自然と表現に現れてきます。
いけばなを通じて、個性を表現するために必要なことは何でしょうか?
いけばなに限らず、個性を表現するためには、まず基礎をしっかり学ぶことが大切だと思います。基礎がしっかりしていないと、どうしても手法が1パターンに偏ってしまいますから。今はYouTubeなどで独学できる方法もありますが、やはり先生について習った方が、情報量が多く技術も身につきやすいです。どの流派を選んでも構いませんが、基礎から学ぶことで、その後の楽しみや可能性が広がると思います。
粕谷さんが考える、「華道の理想の未来」とは?
昔は、花嫁修行の一環でいけばなを学んでいた方が多かったと思います。そういったイメージを払拭し、「クリエイティビティを育てるためには、いけばなをやっておかないとね」という考えが当たり前になる状態まで持っていきたいと考えていますね。例えば、昔の日本では、部屋の用途がひとつに決まっているわけではありませんでした。寝室がなくても、布団を敷けば寝る場所になり、片付けてちゃぶ台を出せば、そこは茶の間になる。ついたてや屏風を置けば、それだけで空間を仕切り、別の部屋のように使うこともできました。そうやって、ひとつの空間を柔軟に使いこなしていたはずなのに、いつの間にか「ここは寝室」「ここはリビング」と用途が固定されるようになり、それ以外の使い方をしづらくなっている気がします。決まった型に縛られることで、発想が硬直してしまっているのではないでしょうか。日本人の良さは、目の前にあるものを生かし、想像力で自在にアレンジする力にある。でも、最近は、それが少し弱まってきているように感じます。「いけばな力」が足りていないと表現してもいいかもしれません。
「いけばな力」! いい言葉ですね。
料理や建築もそうですが、日本人は、もともと他国の文化からエッセンスを抽出し、それを自分なりにアレンジして、まったく新しいオリジナリティを生み出すことに長けていたはずです。いけばなは、そうしたクリエイティビティを育む助けになります。花材の特徴を見極め、その個性をどう引き出すかを考えることは、特別な才能がなくても、誰にでもでき、誰がやってもいいこと。世界中どこへ行っても植物はありますから、その土地ならではのいけばなを生けることができれば、旅の楽しみ方もぐっと広がるのではないでしょうか。
まずは難しく考えずに、いけばなを始めてみることが大切ですね。
体験だけでも構いません。まずは、花を生ける楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。私がいけばなを仕事にしようと決めた時からずっと考えているのは、「この文化を次の世代につなげていくこと」が何より大切だということ。自分をアピールすることよりも、業界全体を盛り上げ、いけばなの魅力を広く伝えていくことのほうが重要だと思っています。そうした思いこそが、活動を続ける原動力になっていますね。
掲載作品について教えてください。
いけばなの本質の一つともいえる「生命の在り方」 に着目し、枯れた花材と生きた花材を組み合わせることで、その境界に潜む“命のうごめき”を表現しています。色を失いながらも、しなやかな曲線を描くアリウムの茎。枯れることで新たな造形美を生み出すオーガスタの葉。水分を失い、変化していくその姿には、むしろ強い“生”の気配が感じられます。そこに、鮮やかな朱色で生命の躍動を象徴するアマリリス、そして生花でありながらくすんだ色彩をもつユーカリを配し、動きと対比を加えました。枯れゆくものと生きているもの。それぞれが放つ異なる生命の質感を重ねることで、時間と存在の狭間にある美を表現しようとした作品です。

PROFILE
華道家/一葉式いけ花四代目家元
粕谷尚弘 Naohiro Kasuya
1980年一葉式いけ花第三代家元 粕谷明弘の二男として生まれる。幼少より家元に師事。大学卒業後、2004年に渡米、インダストリアルデザインを学ぶ。流派内外の花展などに作品を発表し、個展や他の分野の作家とのコラボレーション等を積極的に取り組んでいる。また、海外へのいけばなの普及にも力をいれており、ニューヨーク・メトロポリタン美術館でのデモンストレーションなど、アメリカや南アフリカ、ウクライナ等、数多くのデモンストレーションや指導をするなど、海外での活動も注目されている。