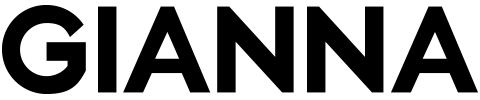華道は、四季の移ろいを尊び、自然の姿をあるがままに捉える、日本独自の美意識を象徴する芸術です。花をいけるという行為は、自己と向き合い、自然とのつながりを深く感じる、精神的な営みでもあります。本企画では、日本を代表する3人の華道家に焦点を当て、彼らが花を通じて表現する独自の世界観を探求します。

一期一会の芸術を紡いで ─ 假屋崎省吾、花に託す記憶と未来
花の個性を見極め、時に器に、時に空間に、その美を昇華させる華道家・假屋崎省吾。幼き日に育んだ庭の記憶、土に込めた命の循環、歴史的建築との融合。そして、幾多の瞬間を重ねて生まれる、一期一会の作品たち——。“美をつむぎだす手”によって命を与えられた花々は、生の輝きをきらめかせ、見る者の心に静かな熱を灯していく。どこまでも自由に、どこまでも真摯に。花と語り合い、空間と共鳴しながら新たな表現に挑み続ける假屋崎は、華道という枠を超えて、普遍的な美のあり方を問い続けている。時代が変わっても色あせない、美の本質を求める旅路に、今、そっと足を踏み入れてみたい。

前号の『GIANNA』をご覧になった際、大胆な柄のオープンカラーシャツに目を留めていらっしゃいました。ファッションと華道、それぞれの美 意識の交差を感じる瞬間はありますか?
私が好きな洋服のブランドは、ポール・スミスです。理由は、花のプリント柄をあしらった服をたくさん手がけているからです。コロナ前までは、直行便でロンドンに飛んで、現地のショップで服をどっさり買い込んでいました。ポール・スミスは、やっぱりクリエイターなんです。これで完成、これで終わりっていうものがない。私も同じで、永遠に進化し続けなくてはいけないという思いがあります。どんどん新しいものを生み出したいという意欲に駆られながら、66歳まで生きてきましたね。
これだけ活躍されていても、まだまだという感覚があるんですね。
手応えを感じたことがないんです。これまで、大きな仕事をたくさんさせていただきましたが、作品を制作している時は夢中で花をいけて、気づけば終わっている。完成した瞬間に、もう過去の作品になるんです。そして、すぐに意識は未来に向いて、「次は違 うものを」「もっとすごいものを」と考え始めるんです。自分がその時点で納得して「はい、完成」と思ったらそれでいいんです。過去には未練がないし、人の評価もあまり気にしない。褒めていただくことも多くてありがたいけれど、いつも、なんとなくこそばゆい思いをしています。そういう意味では、ちょっと特殊な人間かもしれません。
2023年に華道歴40周年を迎えられましたが、花の美しさに気づいた原体験について教えていただけますか。
父は鹿児島県、母は長野県の出身で、2人とも長子ではなく、家を継ぐ必要がなかったので東京に出てきました。その2人が銀座で出会い、私が生まれたんです。子供の頃に住んでいたのは、練馬区・石神井にあった都営住宅。2軒がつながった棟割長屋で、広い庭があったので、両親がさまざまな植物を植えていました。1年中何かしらの花が咲いていて、今振り返るとなんて豊かな環境で育ったんだろうと思いますね。私も見よう見まねで手伝うようになり、園芸少年として育っていきました。
当時は、どんな植物を育てていたのでしょうか?
小学1年生の頃、バラを育てていました。5月の連休が終わった後、丹精込めて育てたそのバラが、ようやく花を咲かせたんです。朝早く庭に出て、バラの花を見た瞬間、もう本当にうれしくて「お母さん、バラが咲いた!」と、急いで母を呼びました。そうしたら、母がハサミを持ってきて、そのバラをチョキンと切ってしまったんです。びっくりしている私をよそに、母はそのバラを新聞紙に包んで「学校に持って行きなさい」とひと言。私は不思議に思いながら登校し、 担任の先生にバラの花を渡したんです。先生は新聞紙の包みを丁寧にほどき、バラの花を牛乳瓶に挿して飾ってくれました。まだ朝早い時間、教室には眠たい空気が漂っていました。目をこすっている子、頬を赤くしている子……そんなクラスメイトたちが、バラの花を見た途端、「はぁー、きれい」と一斉にため息をもらしたんです。母はきっと、感受性の鋭い子供たちに、バラの美しさをおすそ分けしたいと思ったのでしょう。そのことに気づいた時、母のことがすごく誇らしく思えました。
素敵なエピソードをお聞かせいただきありがとうございます。園芸少年として育った假屋崎さんが、いけばなを始められたのは、大学生の時だったそうですね。ご自身にとって、分岐点となった作品はどういうものですか?
大学卒業後、アパレル企業に就職しましたが、「自分はこの世界に向いていないな」と思い、3カ月で辞めてしまったんです。とはいえ、将来の見通しもなく、ハンバーガーショップやスーパーマーケットでアルバイトをしながら、この先どうしようか考えていました。そんな時に、父が亡くなったんです。「何も親孝行ができなかった」と、深く落ち込みましたね。アルバイトをしながらも、いけばなは変わらずに続けていて、都心の画廊にも足繁く通っていました。いつか、画廊で個展をしてみたいと思っていましたが、時給360円のアルバイトでは到底難しい。銀座の画廊を1週間借りると、数十万円かかりますからね。厳しい現実を前にうなだれていた時、母が「これを使いなさい」と言って、老後の蓄えとして貯めていたお金をポンと渡してくれたんです。迷いながらもそのお金を使わせてもらい、神田や銀座の画廊で年に3、4回個展を開催しました。その時に、ただ花をいけてもインパクトがないと考えて、土を使うことを思いついたんです。
土に着目した理由は?
土は、植物の原点です。種をまけば芽が出て、花が咲き、実がなって、枯れた後に再び種が育つ。輪廻転生です。私を花の道へと導いてくれたのは、庭を大切にしていた両親のおかげであり、生きているうちに親孝行をしてあげられなかった父に対する詫び状のような気持ちもありました。そうやって、土を素材にさまざまなテーマで個展を開くうちに、評論家の方が足を運んでくださるようになりました。『美術手帖』という雑誌に取り上げてもらえる機会が少しずつ増えていき、若手の現代美術家として注目されるようになっていったんです。美術館が企画する展覧会に起用してもらったり、花を使ったディスプレイや空間構成、インテリアといった仕事も手がけるようになっていきました。
テレビ出演のオファーを受け始めたのもその頃でしょうか?
1997年に始まった『たけしの誰でもピカソ』というバラエティ番組に出演したことをきっかけに、ほかの番組からもオファーをいただくようになりました。そこから約30年、多くのテレビ番組に出演させていただきました。中でも印象に残っているのは、「50歳を迎えた記念」ということでNHKからオファーをいただき、ジヴェルニーのモネの庭を訪れた時のことです。5日間にわたって庭師さんと一緒に生活し、自分を表現するというドキュメンタリーで、90分の番組にまとめられています。あれは、自分でもいまだに観たいと思う番組ですね。
空間をまるごと使ったダイナミックな作品も多く手がけられていますが、ひとつの作品を仕上げるまでにどのくらい時間をかけますか?
仕事はすごく速いです。いろいろな仕事を経験したおかげで、決断が速いんです。人から何を言われても、いいものはいい、ダメなものはダメ、好きなものは好き。あれこれ迷う時は、ダメだと思って次に行きます。個展も1日か2日で仕上げますね。決断の速さは、作品の花材を選ぶ時だけでなく、家を買う時も同じです。軽井沢の別荘は、電話で詳細をうかがって、物件も見ずに即決しました。
確かな美意識があるからこそ、直感で決断できるのでしょうね。花と建物のコラボレートによる個展「歴史的建築物に挑む」シリーズも開催されていますが、建築に興味を持たれたきっかけについてお聞かせください。
もともとのきっかけは、父が建築関係の仕事をしていたことですね。父が旧華族の邸宅図面や間取り図、写真集などを収集していたので、子供の頃から自然とそういうものに触れていました。両親が旅行好きで、全国各地の神社仏閣やお城などを見せてもらったことも、建築に興味を持つ土台になったと思います。
歴史的建築物など広い空間に花をいける際、花と余白とのバランスをどのように捉えて作品を作っていきますか?
自分の作品をドーンと見せるのではなく、その空間の良さをより一層引き出すようないけ方をします。空間を魅せて、自分の表現も見せる。言うなれば、「融合の美」です。彫刻や絵画は、アトリエで制作したものを会場に運んで展示しますが、いけばなは、その場で素材を組み合わせて、空間と融合させながらつくり上げていくところに醍醐味があります。そうし た制作の過程自体が、ほかの芸術とはまったく異なるものだと思うんです。空間と花と器と自分自身。この4つの出会いを大切にして、瞬間、瞬間で昇華させていきますね。
目黒雅叙園(現ホテル雅叙園東京)では、2016年まで、17年にわたって個展『華道家 假屋崎省吾の世界』を開催されました。
当時は、毎年の恒例行事で、たくさんの方に来場いただきました。目黒雅叙園の「漁樵(ぎょしょう)の間」は、彩色木彫と日本画に囲まれた部屋で、欄間には尾竹竹坡の原図(五節句)が極彩色で施されているんです。この空間の美しさをより引き出せるよう、杜若(かきつばた)の青みがかった紫や、紅葉の赤などに呼応するように、ビビッドに着色した花材などをいけました。
一輪をいける時も、空間全体をデザインする時も、共通して心がけていることは何でしょうか?
「花の持つ力は、作品の大小に関係なく伝わる」というのが私の考え方です。一輪挿しと、空間全体にいける作品の違いは、制作にかかる時間の長さだけ。例えば、島根県大根島の日本庭園「由志園」 で開催した個展では、3.6メートルの角材を200本使って制作しました。高さ5メートル、幅10メートルある大きな作品です。その一方で、ヤツデの葉とダリア一輪だけで表現する作品もあります。どちらも假屋崎省吾のいけばなであり、心の持ちようは変わりません。
先ほど「どんどん新しいものを生み出したい」 とおっしゃっていましたが、作品づくりのインスピレーションはどこから得ていますか?
旅行や建築、それから四季折々の植物。最近は、BLドラマなどの美しい物語からインスピレーションを得ることもありますね。
旅行の際は、どのような場所を巡られるのでしょうか。
旅先で必ず巡るのは、古い建物とお庭です。最近訪れて感動したのは、京都の岡崎にある「對龍(たいりゅう)山荘」ですね。日本の伝統文化を踏襲した素晴らしい建物と庭を見て、大感動して帰ってきました。京都が大好きなので、時間があるとパッと新幹線に乗って、あちこち歩き回っています。
これまで、さまざまな花材を扱われてきたと思います。假屋崎さんにとって、花は雄弁ですか? それとも寡黙ですか?
雄弁ですね。2つと同じものがなく、どの花も自己主張していますから。個性豊かな花材との出会いは奇跡であり、天の恵みのようなものです。そこに自分の 手を加えることによって、新しい美を生み出す。そういう作業をしているんだと思います。
いけている時、どんなことを考えていらっしゃいますか?
花材に向かって「どう?」と尋ねる感じですね。花は物を語りませんが、いけていると「こう見てほしい」という主張が伝わってくるんです。それを否定せず、正直にナチュラルにいける。だから、最初からこういう物を作ろうという構想がないんです。個性を見極めて、素材を生かす。そこに別の素材を組み合わせて、自分らしさをプラスしていきます。
花とセッションしているみたいですね。
花は生きていますから、刻一刻と変化していくわけです。いけばなは「瞬間芸術」であり、まさに、一期一会なんですね。そこに居合わせた人たちだけが体感できて、さまざまな感情を呼び起こされる。人生において、そんな感覚を味わえる瞬間はほとんどありません。とても贅沢なことだと思います。
デジタルの時代における「生の花」の価値につ いて、どのように考えますか?
私はよく「花は心のビタミン」と言いますが、つつましく生活していても、歯を磨くコップに花を一輪挿すだけで空間がうるおって、心の栄養になると思うんです。例えば、戦地ではがれきが散乱し、土の色に覆われていますよね。そのような環境に置かれた時、人の心は荒んでいって、何も感じなくなってしまうと思うんです。そんな荒廃した土地に、つぼみがポンと開くだけで、生命の息吹を感じられるでしょう。そういう感覚が、今の時代にはとても大事だと考えています。
假屋崎さんの作品から、エネルギーをもらっている方も多いと思います。この先、新たに挑戦したいことはありますか?
もっと和の世界を深めていきたいですね。床の間やお茶室のような「枯淡の美」を感じられる空間に、選び抜かれた一輪をいけて、新しい美を生み出すような試みをしたいと思っています。和の世界というのは、やっぱり奥が深いんですよ。命が尽きるまで現役で、完成という概念がない。だからこそ、新しい発想をどんどん生み出していかなければいけないと思っています。
掲載作品について
2018年 假屋崎省吾 個展 第11回「うだつをいける ―美来創生―」作品
赤く実った南天の枝を、空間の広がりを意識しながら大胆に構成。中央には気品あふれる黄色のシンビジウムをいけ、足元には大きな流木を巧みなバランスで設置した、自然美と伝統的な建築を一体化させた作品です。空間全体を包み込むような包容力と静謐な美が宿ってる一作です。写真 増田伸也
PROFILE
華道家/「假屋崎省吾 花教室」主宰 假屋崎省吾 Shogo Kariyazaki
東京都出身。独特の色彩感覚と繊細かつダイナミックな作風で、 美輪明宏氏より「美をつむぎだす手を持つ人」と評され、各国賓の来日歓迎装花、天皇在位10年周年記念式典や、天皇退位・即位の特別番組スタジオ花装飾などを手掛ける。着物、花器、棺、骨壷の デザイン・プロデュースをおこない、ライフワークでもある花と建物のコラボ個展“歴史的建築物に挑む”シリーズを世界遺産・国宝・ 重要文化財で開催。少子化問題や花育などの社会活動も取り組み、ますます卓越した存在感を放ち続けている。
Edit:RYOTA KOUJIRO Text:SUI TOYA