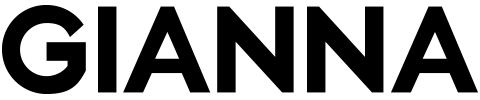華道は、四季の移ろいを尊び、自然の姿をあるがままに捉える、日本独自の美意識を象徴する芸術です。花をいけるという行為は、自己と向き合い、自然とのつながりを深く感じる、精神的な営みでもあります。本企画では、日本を代表する3人の華道家に焦点を当て、彼らが花を通じて表現する独自の世界観を探求します。

花で描く時代の輪郭 ─ が示す、次代の美意識
花や枝が空間に息づき、その存在感を余白の中に静かに託す。いけばなは、ただ「飾る」ものではなく、極めて深遠な表現の形である。そんな世界に新たな光を当てる華道家・大谷美香。伝統に敬意を払いながらも、常に「まだ見ぬ美」を求め続ける、新しい時代の表現者だ。いけばなを“場の芸術”として捉え、空間そのものを編み直すような創作は、まさに現代アートと呼ぶにふさわしい。枝の線を際立たせる余白、疎と密の調和、そして日本の自然観を宿す美意識──その一つひとつに彼女の哲学が宿る。「空間を埋めるのではなく、空間を創る」こと。その静かで力強い信念に迫りたい。
数ある日本文化のなかで、華道を選ばれたのはなぜでしょうか?
19歳でイギリスに留学した時、日本のことをよく聞かれました。中学生の頃から茶道を習っていて、大学では箏曲部にも入っていましたが、「日本文化の良さって何?」と改めて聞かれると、うまく答えられなくて……。そのような経験から「もっと自分の国のことを知りたい」と考えるようになり、新しく和の習い事をしたいという思いが強くなっていきました。帰国した後、ふと思い出したのが、茶道の時に茶室に飾ってあったお花のこと。「そうだ、華道をやってみよう」と、本当に軽い気持ちで家の近くのお教室に通い始めたことが、すべての始まりでした。
その時に出会ったのが、草月流師範の富田双康先生だったんですね。師匠から受け継いだ、今も大切にしている教えはありますか?
いけばなには数百もの流派があり、それぞれ考え方が異なります。伝統的な様式を大切にする流派もありますが、草月流はその対極にある存在。とても前衛的で、「今を生きる花をいけなさい」という教えを大切にしています。私の師匠もとてもクリエイティブな方で、石膏などを用いて色々な作品を作られていました。そんな師匠からよく言われたのは、「君にしかできない表現をしなさい」「アートとして新しいアイデアを入れなさい」ということ。そう言われると、やはり挑戦心が湧いてきます。「こういうのはどうだろう」「ああいうのも面白いかも」という風に、試行錯誤を重ねた日々が、今も自分の力になっていると思います。
大谷さんは、ご自身の作品を発表するほか、数多くのドラマや映画でいけばな装飾を手がけていますね。「自分らしい華道」とは、どのようなものだと思いますか?
新しい表現を模索している華道家はたくさんいますが、私はその中でもチャレンジャーな方だと思っています。新しい表現は模倣され、やがて定番になっていく——それはアートの宿命のようなものです。草月流の表現も、華道全体で見れば革新的ですが、流派のなかでは既に定番化している表現もあります。だからこそ、現状にとどまらず、恐れずに挑戦し続ける。それが、私らしい華道だと考えています。
新しいことに挑戦することは怖くありませんか?
プライドや羞恥心よりも、「とにかくやってみよう!」 という気持ちの方が勝ります。アートの先駆者たちから、そうした前向きな勢いを分けてもらうことも多いですね。今でこそ巨匠と呼ばれる画家や彫刻家たちも、新しいことを始めた当初は、批判を受けていました。その批判をバネにして、自分の表現を貫いた時に、本当の“新しさ”が目を覚ます。美術館の解説パネルや音声ガイドなどでそうした背景を知ると、「多少の批判なんて恐れなくていい。自分も挑戦していいんだ」と、すごく励まされます。
最近、ご自身のなかで「新境地を切り拓いた」と感じたお仕事はありますか?
昨年(2024年)、中国からご招待をいただき、北京から車で3時間ほどの距離にある高級リゾート地で、いけばなパフォーマンスを行いました。舞台となった「Aranya金山嶺音楽堂」は、中国でアートの発信地として知られる有名なホール。ここに立つことは、中国のアーティストにとって憧れなのだそうです。そんな場所でパフォーマンスをさせていただけることは光栄ですし、新しい表現を見ていただくチャンスだと思い、「巨大ないけばなが、いけ上がっていく様子をお見せします」とお伝えしました。ところが、担当者から返ってきたのは「それではエンタメ性に欠ける」という言葉。「お客様は新しくて面白いものを期待してチケットを購入されるのに、それは本当に新しいのか?」と言われたのです。
思いもかけない言葉ですね。
私は、大きな作品や、その作風自体が新しいものだと思っていたので、目から鱗でした。どうすれば、より新しい表現を見せられるか? そこで考えついたのが、いけばなをエンターテインメントショーのように演出することでした。山の女王が精霊たちを目覚めさせ、花を咲かせるというストーリーを考案し、私を含めたキャスト全員が、舞いながら花をいける様子をお見せしました。
今年の4月にも、中国・杭州のリゾート施設でパフォーマンスをされていましたね。
昨年のパフォーマンスが非常に好評だったことを受けて、杭州の「富春山居」というリゾート地からオファーをいただきました。舞台となったのは、25 ×25mの室内プール。水を10cmほど張り、その水を跳ねさせながら舞い踊って、花をいけるというパフォーマンスを披露しました。ストーリーもアップデートし、昨年より良いパフォーマンスができたと自負しています。「いけばなで、こんなこともできる」という可能性を追求していく意欲が、より一層高まりました。
新しい表現のヒントは、どのようなところから得るのでしょうか?
いけばなは「場にいける」と言われていて、場所が決まってから構成を考えます。例えば、いける場所が部屋の中央であれば、全方向から見られるように構成します。また、壁際であれば、正面と横の見え方を意識して構成します。私の場合は、その場所に立ち、「こういう花をいけたらどうだろう」と、頭の中でラフスケッチを描くことから始めます。そのラフに従って、実際に花材を手に取りながら、より自分らしいいけ方になるよう調整していきます。中国・杭州でのパフォーマンスの際は、この調整に時間をかけました。事前に「25×25mのプール」が舞台ということは聞いていましたが、実際にそこに立ってみると、想像以上に広大な空間で。この空間に負けない作品を作らなければと思い、調整を重ねるうちに、作品がどんどん巨大化していきました。最終的には、いけばなというよりも、まるで3つの大きな山がそびえ立っているかような作品に仕上がりました。
場所のほかに、普段どのようなものからインスピレーションを得ていますか?
建築からインスピレーションを得ることがあります。面白い建築物を見かけると、「あの構造をいけばなで表現できないかな」と考えることも。また、メイクからアイデアのヒントを得ることもあります。メイクは、表現できる範囲が限られていて、限られたスペースのなかで線を引き、さまざまなカラーを重ねていきます。その工夫の積み重ねに惹かれるのです。パフォーマンスの際に、アート的なメイクを取り入れたら面白いかもしれないと思い、シュウ ウエムラの店 舗で、色々なメイクを試していただいたことがありました。線の入れ方ひとつで顔の印象ががらりと変わる様子を見て、心が躍りましたね。
建築もメイクも、いけばなに通じるところがあるんですね。花をいける時、「余白」の取り方についてはどのように考えられていますか?
いけばなでは、線を大切にするという考え方があります。見る人に「この枝の線が美しい」と感じてもらうためには、枝の下に余白が必要です。例えば、枝が長く伸びている場合、その枝の下が取るべき余白となります。ここを何かで埋めてしまうと、線の美しさが損なわれてしまいます。
余白があるからこそ、線の美しさが際立つということでしょうか。
その通りです。もうひとつ大切なのは、「疎密」の強弱を考えることです。余白を多く取って「疎」にする部分がある一方で、花をギュッといけて「密」にする部分もある。疎密をどう見せるか、大きな作品の場合は特にバランスが難しくなります。
大谷さんは、海外でのお仕事も数多くこなされていますが、世界の人々に伝えたい「日本の美意識」とは何だと思いますか?
海外のフラワーアレンジメントは花がメインで、アクセントとして葉や枝を用います。一方で、日本の華道は、自然を丸ごと愛すという考え方が基本。それは、どの流派も同じです。花も葉も枝も、すべて貴重でかけがえがないという美意識は、海外の方にもぜひ伝えたいと思っています。
海外で日本のいけばなの感覚が伝わらず、苦労した経験はありますか?
西洋のフラワーアレンジメントはケータリングに適した形ですが、いけばなは持ち運びができません。空間の大きさや場の雰囲気を確かめてからいけるので、「ほかの場所では制作できない」「一度いけたら動かせない」ということを伝えるのに、苦労することが多いです。
フラワーアレンジメントは、花器やカゴなどに、花を「密」に飾りつけるイメージがあります。余白の感覚も、日本と海外では異なるのではないでしょうか?
そうですね。「空間を埋める」というのが、フラワーアレンジメントの根本的な考え方です。1平方メートルの空間があれば、そこを花でしっかり埋めます。海外に行くと「美香の作品は、1平方メートルあたりいくら?」とよく聞かれます。ただ、私の作品は、一方は花で埋まっているけれど、もう一方は枝1本だけという場合もあるため、1平方メートルあたりの価格を尋ねられても困ってしまう。なので、そう聞かれた時はいつも「空間を埋めるのではなく、空間を創るのです」と答えるようにしています。
その感覚が伝わらない時はどうしますか?
海外では、いけばなに対する固定概念がないので、作品を見せるとすぐに納得していただけることが多いです。いけばな=日本のフラワーアートという認識で私を迎えてくださるので、「あなたのアートを作ってください」と、任せていただけることがほとんどですね。そういった意味では、海外の方が気楽に、自由に活動できる感覚があります。
日本で仕事をする時の方が、苦労することが多いですか?
日本では「いけばなは侘び寂びの世界」といったイメージが根強く、いけばなと聞くと、床の間に飾るような作品を思い浮かべる方がほとんどです。もちろん、そういった伝統的な作品もありますが、私がいけているのは、現代の空気を取り入れた新しい時代の花です。いけばな人口を増やしていくためにも、「いけばなはアート」という認識を広げていきたいと思っています。映画やドラマ、舞台のお仕事に携わるのは、より多くの方にいけばなを知っていただくためでもあります。
2018年のドラマ『高嶺の花』(日テレ)では、174点もの作品を制作されたそうですね。最近も、『1122いいふうふ』(Amazon Prine Video)、 『地面師たち』(Netflix)など、話題作のいけばな監修を多数手がけられています。
昔は、映画やドラマのスタッフの方から、「これは、いけばなですか?」と不思議そうな顔をされることがよくありました。最近は、「大谷美香のいけばな」を理解していただけるようになり、挑戦しがいのある テーマを与えていただける機会が増えて、ありがたいと感じています。「胡散臭い花を作ってください」「殺りくを表現してください」など、自分では考えつかないようなテーマを与えられるとワクワクしますし、制約の中でどれだけ表現できるか、自分に挑むような気持ちになります。
映画・ドラマ・舞台のお仕事のほかに、いけばなを広めるための活動はされていますか?
2023年から、北海道・函館市の「金森赤レンガ倉庫」で、インスタレーションを行うようになりました。函館で育った花を、函館にお住まいの方、函館を訪れた方など、ゲストの皆さんにいけていただくイベントです。花をいける喜びを伝えたいと思って言葉を尽くしても、なかなか伝わらないことがもどかしくて。それならば、体感していただくのが一番だと思い、このようなイベントを定期的に開催しています。2023年は、1000人のゲストに、アルストロメリア1000本をいけていただき、1つの作品に仕上げました。さまざまな世代の方が、楽しそうに参加してくださり嬉しかったです。今年は、ひまわりを700本いける予定です。
素敵な取り組みですね。創作を続ける中で、日頃から大切にしている習慣はありますか?
「花を粗末にしないこと」です。撮影や取材でいけた花は家に持ち帰り、簡単にいけ直します。花を枯らしたり、粗末に扱ったりすると、いざという時に力になってもらえない気がするので。いわば私のジンクスです。パフォーマンスなど大きな仕事の前は、使用する花材に向かって「今日もよろしくね」と、こっそり挨拶をしています。
掲載作品について
作品タイトル「花笑む。」大地の芸術祭 越後妻有 アートトリエンナーレ 出品作品
力強い大地から、新しく生まれて咲き誇る「希望の花」。希望という太陽に向かい枯れることなく咲く花。大地から途絶えることのない夢を吸い上げ伸びる枝。生け花をアートとして表現。

PROFILE
華道家/草月流一級師範理事 大谷美香 Mika Otani
1990年草月流入門。初代蒼風家元の直門・故富田双康先生に師事。いけばな教室「アトリエ双香」主宰。映画・ドラマ・舞台での装 飾も数多く担当し、国内だけにとどまらず世界で活躍中。そのイノベーティブで芸術的な表現は多くの見る人の心をつかみ、新しい日本文化の真骨頂といえる。
Edit:RYOTA KOUJIRO Text:SUI TOYA